
「再生医療にはどんな種類があるんだろう?」
「いろいろな病気に効くというけれど、治せる病気にはどんなものがあるの?」
この記事を開いたあなたは、そんな疑問を抱いているかもしれません。
再生医療が治療できる病気の種類は、実に幅広く数多いものです。
がん、糖尿病、肝硬変、脊髄損傷、やけどの皮膚再生、角膜の再建などはすでに厚生労働省の認可を受け、保険適用または保険と自己負担併用で治療を受けられます。
また、自由診療でよければ、肌質改善やしわ改善などのアンチエイジング美容、脱毛の人向けの毛根再生、乳がん切除後の乳房再建なども行われています。
そこでこの記事では、
◼️現在受けられる再生医療の種類
を、保険適用とそうでないものなどに分類し、病名や治療法をリスト化しました。
さらに、
◼️現在研究中の再生医療の種類
◼️リスクの高さによる再生医療の分類
なども紹介し、再生医療におけるさまざまな「種類」について解説していこうと思います。
この記事を読んで、再生医療に対するあなたの疑問が解消されることを願っています。
1. 現在受けられる再生医療の種類

再生医療は、幹細胞の再生能力を生かして、病気やけがを身体の中から根本的に治療しようというものです。歴史の新しい医療であるため、現在でもまだ研究段階にある治療法が多く、誰でも病院へ行けば受けられる治療の種類は限られています。
それらは以下の3種に分類することができます。
1)国の承認を受けて保険適用されている治療
2)先進医療として認められ一部保険適用される治療
3)自由診療(全額自己負担)で受けられる治療
では、3種それぞれについて説明していきましょう。
1-1. 国の承認を受けて保険適用されている治療
まず、国の承認を受けて保険適用されている治療は以下のものです。(2020年6月現在)
| 国の承認を受けている治療 |
|---|
・造血幹細胞移植後の急性移植片対宿主病 <条件及び期限付き承認> |
再生医療については、厚生労働省が所管しています。
まだ新しい医療であるため、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」という法律を定めて、各治療の有効性と安全性を確保できるようさまざまな手続きやルールが設けられています。
まず、再生医療の研究や治療を行おうとする医療機関や研究機関は、その内容を厚生労働省に届け出て受理されなければなりません。
そして、研究や治験を経て治療の安全性と有効性を厚生労働省が確認したものに対しては、保険が適用されることになります。
つまり、保険適用されている再生医療は、国が認めた安全で有効な治療だといえるのです。
ただ、現在のところ保険適用される再生医療の種類は多くはありません。
冒頭の表にあげた疾患に対する治療のみです。
一方で、再生医療に対する期待は非常に高く、「自分が罹患している病気に対しても、早く保険適用で再生医療が受けられるようになってほしい」と切望している患者も多いのが実情です。
そこで、有効性が推定され、安全性が確認されたものについては、「条件および期限付き」で早期に承認、保険適用できる制度が設けられました。
上の表で「<条件及び期限付き承認>」のリストにあがっている疾患の治療がそれにあたります。
ただ、これらは承認後にあらためて有効性と安全性の検証がなされる必要があり、そのため「拙速な承認はいかがなものか」という疑問や批判がの声があることも知っておくべきでしょう。
いずれにしても、まだまだ研究途上の治療法が多い再生医療の中で、いち早く一般化されたのがこれらの治療だというわけです。
1-2. 先進医療として認められ一部保険適用される治療
次に、「先進医療」として国に認められ、一部に保険が適用される治療は以下です。(2020年6月現在)
| 先進医療と認められている治療 |
|---|
・胸髄損傷 |
「先進医療」というと、漠然と「一般的な治療よりも進んだ最新の医療」のようなイメージを持つかもしれませんが、実際には以下のように明確な定義があります。
健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)において、「厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、保険給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養」として、厚生労働大臣が定める「評価療養」の1つ
(中略)
将来的な保険導入のための評価を行うものとして、未だ保険診療の対象に至らない先進的な医療技術等と保険診療との併用を認めたものであり、実施している保険医療機関から定期的に報告を求める
厚生労働省ホームページ「先進医療の概要について」より引用
簡単に言えば、広く一般的に行われている標準治療とはまた別に、
・厚生労働大臣が「先進医療」として承認したもの
・まだ保険適用されない先進的な医療であるが、保険診療との併用が認められている
・将来的には保険適用をするかどうかの評価を行う
ということです。
再生医療の中でこの「先進医療」として認められているのは、前掲の表にあげた疾患の治療のみです。(2020年6月現在)
これらの治療は、その治療を行うことを厚生労働省に届け出て認められた医療機関で受けることができます。
その際は、全体の治療のうち先進医療にあたる部分は保険適用外なので全額自己負担ですが、それ以外の通常の治療にあたる部分(診察、検査、投薬、入院など)には保険が適用されます。
1-3. 自由診療(全額自己負担)で受けられる治療
そして、保険は適用されず、自由診療として全額自己負担で受けられる治療は、以下のものなどさまざまです。(2020年6月現在)
| 自由診療で受けられる治療 |
|---|
・がん |
前述の2項の再生医療は保険適用に関わるため、厚生労働省が認めている治療の種類は限られています。
が、保険適用外でも構わないのであれば、もっとさまざまな疾患に対する再生医療が行われているのが実情です。
がんや肝硬変といった深刻な病気の治療だけでなく、中には
◎乳がんなどで失われた乳房の再建
◎脱毛症の改善
◎肌質改善、しわ治療
なども実施されています。
再生医療は人間に健康を取り戻させるだけでなく、QOL(クオリティ・オブ・ライフ=生活の質)の向上にも大きく寄与するものだと言えるでしょう。
ただ、これらは自由診療ですから、費用は全額自己負担で、治療内容や医療機関によっては非常に高額になってしまう可能性があります。
また、保険適用のものや先進医療と認められたものとは違って、国によって有効性が確認されていない治療だということも理解しておく必要があるでしょう。
参考:再生医療等提供機関一覧(各種申請書作成支援サイトで登録されているもの)(厚生労働省)
参考:再生医療ポータル(一般社団法人日本再生医療学会)
参考:独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ「新再生医療等製品の承認品目一覧」
参考:先進医療の概要について(厚生労働省)
2. 現在研究中の再生医療の種類

1章であげた再生医療は、現在医療機関で受けることができるものです。
一方で、今後の患者への治療実施を目指して、医療機関や大学などの研究機関で研究が続けられている再生医療も数多くあります。これらは研究の段階によって、以下の3種に分類することができます。
1)臨床治験(国からの承認を目指し、実際にヒトに治療や投薬を行う試験)を行っている治療
2)臨床試験・臨床研究(治験以外)を行っている治療
3)大学などの研究機関で研究中(まだヒトを対象にしていないなど)の治療
それぞれどんな治療の研究が行われているのか、説明していきましょう。
2-1. 臨床治験を行っている治療
現在、ヒトに対して臨床治験が行われているのは、以下のものなどがあります。(2020年6月現在)
| 治験を行っている治療 |
|---|
・脳梗塞 |
臨床治験とは、厚生労働省から承認を受けることを目指して、実際に人に対して治療や投薬を行う試験のことです。
現在臨床治験が行われている治療は数多く、上の表であげたのはその一部です。また、今後さらに新しい治療法や薬品についての治験も増えていくでしょう。
もし、
「この表にある◯◯病の再生医療とは、どんなものだろう?」
「自分の罹患している病気についても再生医療の治験が行われているようだけれど、自分も受けられないだろうか?」
「これ以外にどんな治験が行われているのだろう?」
といった疑問や希望があれば、以下のサイトを参照してください。
◾️再生医療等提供機関一覧(各種申請書作成支援サイトで登録されているもの)(厚生労働省)
厚生労働省の承認を受けた、再生医療を実施している医療機関・研究機関のリストです。
検索機能はありませんが、再生医療を行なっている医療機関の名称・所在地などの情報と、治療の内容や資料などを閲覧することができます。
◾️再生医療ポータル(一般社団法人日本再生医療学会)
日本再生医療学会が、再生医療の情報を広く知らせるために運営しているポータルサイトで、再生医療についてさまざまな情報を得ることができます。
特に、「提供機関をさがす」というページでは、
・自由診療を行なっている医療機関
・臨床研究を行なっている医療機関、研究機関
のデータベースを検索できるようになっています。
地域、診療科、治療法、病名、部位などで検索することができるので便利です。
◾️臨床研究情報ポータルサイト(国立保健医療科学院)
患者や一般の人向けに、現在行なわれている臨床研究や治験の情報を提供するポータルサイトです。
フリーワードで検索でき、「参加者募集中」「一般募集中」など進捗状況でも絞り込むことができるので、「この疾患についてこれから参加できる治験を探したい」などという際に利用できます。
ただ、再生医療に限らずさまざまな研究が含まれるので、試験のくわしい内容を確認する必要があります。
本来は、厚生労働大臣に対して実施計画の提出などの届出手続を行うためのシステムですが、「臨床研究検索」のページではこれまで届出された研究や治験を検索することができます。
疾患名、「募集中」「研究終了」などの進捗状況、フリーワードなどで絞り込むことができ、研究のくわしい内容も知ることができます。
医薬品や医療機器などの有効性、安全性にについて指導・承認審査する「医薬品医療機器総合機構」のホームページです。
中に「治験情報の公開」というページがあり、最近までに届け出があった主な治験情報を公開しています。
検索機能はありませんが、リストをPDFかExcelでダウンロードすることができます。
2-2. 臨床試験・臨床研究を行っている治療
次に、臨床試験や臨床研究段階にあるのは、以下のようなものがあります。(2020年6月現在)
| 臨床試験・臨床研究中の治療 |
|---|
・加齢黄斑変性 |
人を対象にした研究のうち、治験以外の段階にあるもので、この表にあげたのはその一部です。
これらの中にも治験と同様、患者が参加できるものがありますので、興味があれば前述した情報サイトで調べてみてください。
2-3. 研究機関で研究中の治療
そして、大学などの研究機関で研究中のものです。(2020年6月現在)
| 研究機関で研究中の治療 |
|---|
・歯、外分泌腺などの立体形成 |
3. リスクの高さによる再生医療の分類

ところで再生医療はまだ新しい医療技術であり、その治療効果が期待される一方で、治療の内容によっては人の命や健康に影響を与える懸念もあります。
そのため、「1-1 国の承認を受けて保険適用されている治療」でも触れた「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」という法が定められました。
この法律では、再生医療をリスクの高さによって以下の3段階に分類しています。
「再生医療の種類」といえば、この3種を指す場合も多いので、知っておいてください。
| 分類 | リスク | 定義 | 具体例 |
|---|---|---|---|
| 第一種再生医療等技術 | 高 | 人の生命及び健康に与える影響が明らかでない又は相当の注意をしても人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあることから、その安全性の確保等に関する措置その他のこの法律で定める措置を講ずることが必要なものとして厚生労働省令で定める再生医療等技術 | ES細胞やiPS細胞を利用した医療など |
| 第二種再生医療等技術 | 中 | 相当の注意をしても人の生命及び健康に影響を与えるおそれがあることから、その安全性の確保等に関する措置その他のこの法律で定める措置を講ずることが必要なものとして厚生労働省令で定める再生医療等技術(第一種再生医療等技術に該当するものを除く。) | 体性幹細胞を利用した医療など |
| 第三種再生医療等技術 | 低 | 第一種再生医療等技術及び第二種再生医療等技術以外の再生医療等技術 | 体細胞を加工する医療など |
「再生医療等の安全性の 確保等に関する法律について」厚生労働省
では、それぞれについて簡単に説明しましょう。
3-1. 第一種再生医療等技術
「第1種再生医療等技術」は、現在ではまだ安全性の確認が十分でなく、人に対して実施するに至っていないものなど、リスク程度はもっとも高い医療です。
実は「再生医療」として大きな期待を集めている「ES細胞」や「iPS細胞」による医療はこの第1種に含まれます。
現・京都大学iPS細胞研究所所長である山中伸弥教授が2012年にノーベル生理学・医学賞を受賞したことで一躍注目されたiPS細胞ですが、まだヒトに対しての臨床試験例はごく少ないのが現状です。
ES細胞も、日本での離床試験は2019年にはじめて行われたばかりで、これらの臨床試験、そして臨床応用の充実が待たれています。
3-2. 第二種再生医療等技術
第二種に分類されるのは、再生医療の中でもリスクが中程度のもので、その代表は体性幹細胞を用いた治療です。
幹細胞を利用した再生医療において、現在ヒトに対して実施されている治療や試験はすべてこの体性幹細胞を用いたものですから、治療を受ける際にはリスクについてくわしく確認することが必要だと言えるでしょう。
3-3. 第三種再生医療等技術
再生医療の中でもっとも安全性が高いのが、第三種に分類される治療です。
主な例としては、活性化リンパ球を用いた従来の各種がん治療が挙げられます。
これは患者自身から採取した細胞を移植する「自家移植」なので拒絶反応がなく、治療の実施例も多いため低リスクなのです。
ただ、いずれにしろ再生医療は人体に対してリスクゼロではありません。
治療を受ける際には、医療機関からくわしい説明を受け、インフォームドコンセントを行ってもらうようにしてください。
参考:「再生医療等の安全性の 確保等に関する法律について」(厚生労働省)
参考:「再生医療等安全確保法案について」(文部科学省)
参考:再生医療について(厚生労働省)
4. 再生医療に利用される主な幹細胞の種類
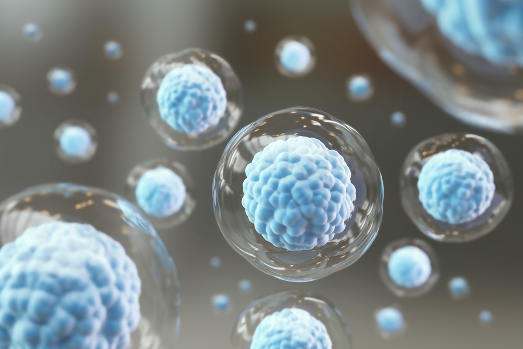
また、再生医療に用いられる幹細胞は1種類ではありません。
現在では主に、
・体性幹細胞
・ES細胞
・iPS細胞
の3種を用いる方法があります。
「iPS細胞」は、現・京都大学iPS細胞研究所所長である山中伸弥教授が発見し、2012年にノーベル生理学・医学賞を受賞したあの細胞です。
これら3種にはそれぞれ特長、メリット・デメリットがあります。
以下の表に簡単にまとめてみました。
体性幹細胞 | ES細胞 | iPS細胞 | |
|---|---|---|---|
| 作製方法 | ヒトの身体に自然に存在する | 受精卵が数回分裂したあとの細胞のかたまり=「胚」から細胞を取り出し、培養する | ヒトの皮膚や血液などの細胞に、特定の4つの遺伝子を導入して培養する |
| 特長・能力 | 特定の種類の細胞に分化が可能 | すべての種類の細胞に分化が可能=多能性幹細胞 | すべての種類の細胞に分化が可能=多能性幹細胞 |
| 移植の適合性 | 患者自身の細胞を用いるので、免疫拒絶反応が起こらない | 他人の細胞から作られるため、免疫拒絶反応が起こるリスクがある | 他人の細胞からも患者自身の細胞からも作ることができ、免疫拒絶反応が起こるリスクは低い |
| 倫理的な問題 | 患者自身の細胞を用いるので、問題はない | 受精卵を使うため、ヒトの命に操作を加えることが問題視される | 皮膚や血液などありふれた細胞を用いるので、問題はない |
| 臨床上の課題 | ・体内に存在する数が少ない | ・腫瘍化、がん化のリスクがある | ・腫瘍化、がん化のリスクがある |
| 臨床の現状 | 現在一般的に実施されている幹細胞を利用した再生医療は、基本的には体性幹細胞を用いたもの | 海外で臨床試験あり | 2014年に日本で世界初の臨床手術を実施 |
では、3種それぞれについてくわしく説明しましょう。
4-1. 体性幹細胞
体性幹細胞は、私たち「ヒト」の身体の中に自然に存在する幹細胞で、造血幹細胞、脂肪幹細胞、表皮幹細胞、神経幹細胞などの種類があります。
幹細胞なので自己複製能と多分化能を持っていますが、その能力は限定的です。それぞれの幹細胞が分化できる細胞の種類は限られており、分裂できる回数にも限りがあります。
主な幹細胞が分化できる細胞は以下の通りです。
・造血幹細胞:骨髄の中に存在し、白血球、赤血球、血小板など血液細胞に分化する
・脂肪幹細胞:脂肪組織の中に存在し、さまざまな細胞に分化できる
・表皮幹細胞:肌の表皮に存在し、皮膚を作る表皮角化細胞を作り出す
・間葉系幹細胞:骨髄、脂肪組織、胎盤組織や臍帯組織などさまざまな組織から採取でき、間葉系に属する細胞(骨芽細胞、脂肪細胞、筋細胞、軟骨細胞など)に分化する
再生医療で利用される際には、患者自身の身体から採取した体性幹細胞を体外で培養し、患者の身体に移植するため、免疫拒絶反応が起こらないという大きなメリットがあります。
現在一般的に行われている幹細胞を用いた再生医療は、基本的にはこの体性幹細胞による治療です。
4-2. ES細胞
ES細胞は、受精卵が6〜7日経って数回分裂してできる「胚」から細胞を取り出し、それを培養することで人工的に作られる「多能性幹細胞」のひとつです。1981年にはじめてのマウスES細胞が作られました。
発生初期の胚から作られるため未分化(=まだ役割が決まっていない細胞)で、受精卵に近い高い自己複製能、多分化能を持っているのが特長です。
人間の身体のあらゆる組織の細胞に分化することができ、分裂回数もほぼ無限であるため「万能細胞」とも呼ばれています。
1998年にアメリカのチームがヒトES細胞の作製に成功すると、2007年に京都大学の山中伸弥教授によるヒトiPS細胞が登場するまで、再生医療の中心と担う幹細胞として期待を集めていました。
ただ、万能細胞である反面、大きな課題も抱えています。
ひとつは、胚から作られるため、患者は他人の細胞を移植されることになるという点です。
自家移植である体性幹細胞治療に対して、ES細胞は他家移植であるため、免疫拒絶反応を引き起こすリスクが避けられません。
さらに、材料となるのが「胚」であることも問題視されています。
胚はこれから分裂を繰り返せば、やがて生物になるはずのものです。
つまり「命の萌芽」とも言えるもので、それを壊してES細胞を作ることは倫理的に問題なのではないか、と議論が巻き起こったのです。
ヒトES細胞の材料となる胚は、不妊治療の際に必要なくなったもので、ドナーの同意も受けていますが、それでもこの議論は根強く、ES細胞の臨床応用が進まない一因となっています。
4-3. iPS細胞
iPS細胞は、ヒトの皮膚や血液などの細胞から人工的に作られる「多能性幹細胞」です。
ヒトの身体のあらゆる細胞に分化することができ、分裂回数もほぼ無限の「万能細胞」であることは、ES細胞と同様です。
が、未分化の細胞から作られるES細胞とは異なり、iPS細胞は分化済みの成熟細胞を材料としています。
採取した成熟細胞に特定の遺伝子4つを取り込ませることで、未分化の幹細胞だった状態に初期化(=リプログラミング)することができるのです。この4つの遺伝子は、発見者の山中教授の名を冠して「ヤマナカファクター」と呼ばれています。
iPS細胞は、ES細胞の抱えるふたつの課題を解決する存在として注目を集めました。
まず、自家移植ができるので、免疫拒絶反応のリスクは低くなります。
そして、ヒトの成体から採取した細胞で作るので、倫理的な問題もありません。
まだ発見から日が浅く、品質が安定しない、がん化のリスクがあるなど課題はいろいろとありますが、今後の臨床試験に期待が集まっています。
参考:「身体のはじまりを知る―幹細胞のはなし―」小川亜希子(生物工学会誌 第94巻第5号、2016年)
参考:「iPS 細胞の可能性と今後の課題」高橋 政代(学術の動向 第14巻第8号、2009年)
参考:「再生医療の現状と問題点」中畑龍俊(炎症・再生 第24巻第2号、2004年)
参考:「『臨床応用』における幹細胞の特徴 比較」厚生労働省
参考:「先天性尿素サイクル異常症でヒトES細胞を用いた治験を実施―ヒトES細胞由来の肝細胞のヒトへの移植は、世界初!―」国立成育医療研究センター 日本医療研究開発機構
5. まとめ
いかがでしたか?
再生医療の種類について、さまざまな角度から理解できたかと思います。
では、最後に記事の内容を振り返ってみましょう。
◎現在受けられる再生医療は、以下の3つに分類できる
・国の承認を受けて保険適用されている治療
・先進医療として認められ一部保険適用される治療
・自由診療(全額自己負担)で受けられる治療
◎リスクの高さによる再生医療の分類は、
・第一種再生医療等技術
・第二種再生医療等技術
・第三種再生医療等技術
◎再生医療に利用される主な幹細胞の種類は、
・体性幹細胞
・ES細胞
・iPS細胞
これらの知識をもとに、あなたが再生医療についてより一層理解を深められることを願っています。
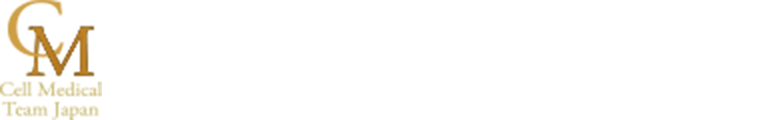
- コメント -